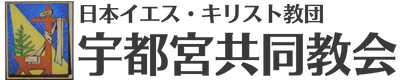待降節礼拝説教
マリアとエリサベツ、この二人はいずれも子を身ごもっている妊婦です。二人の身ごもりについては特別な経緯がありました。エリサベツは、子を産むことなく年をとっていました。聖書はエリサベツが「不妊だった」と記しています。そのエリサベツの夫であるザカリアは、天使からこう告げられていました。
「あなたの妻エリサベツは、あなたに男の子を生みます。その名をヨハネとつけなさい。」
一方のマリアは、婚約者がいましたがまだ結婚はしていない身でした。聖書はマリアを「処女」と記しています。そのマリアもまた天使からこう告げられていました。
「あなたは身ごもって、男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。」
エリサベツの身ごもりも、マリアの身ごもりも、それは天からの告げられたことばによる、すなわち神さまの約束によるものでした。そして事実、この約束の通りに二人は身ごもりを体験することになったのでした。
エリサベツにとってもマリアにとっても、実際に自分が身ごもったことが分かったときは、たいへん驚いたことでしょう。そして二人は母になるという喜びもあったでしょうが、それ以上に、告げられていたことばのとおりに自分の胎に生じている命を感じながら、神はまことにおられるという畏れと喜びに満たされていました。
この二人の喜びは人間がつくりだしたものではなく、神さまによってつくりだされた喜びであったといえます。このような喜びに満たされているマリアとエリサベツの姿を想起することは待降節(アドヴェント)の礼拝にふさわしいことです。というのも、まもなく迎えますクリスマスは、二人の女性たちの喜びと同じように神さまだけがつくり出すことのできる喜びを受け、祝うものだからです。
人間がつくり出す喜びには良いものがたくさんありますが、その多くは一時的であり、色褪せてしまいやすいものです。また本来、人として喜ぶべきではない、後ろめたい喜び、偽りの喜びということもあります。それに対して神さまがつくり与えてくださる喜びは永遠であり、人をいきいきと活かすものとなります。
◆
二人から生まれてくる子には、それぞれ、ヨハネとイエスという名が定められていました。エリサベツから生まれるヨハネは、マリアから生まれるイエス、すなわちキリストに先駆けて伝道をはじめ、キリストの証人として「見よ、世の罪を取り除く神の子羊」(ヨハネの福音書第1章29節) と語る人になります。このヨハネとイエスによって新しい時代が始まろうとしていました。
しかし、山里の町でマリアとエリサベツが出会っていた時、二人が目にし、生活していた社会は、あいかわらず貧しく、ユダヤ人を支配しているローマ政府に対する不満は深まるばかりでした。新しい時代の幕開けなどという希望はどこにもなかったのです。
12月になるとこの1年に起こった大きな出来事を数えあげることがよく行われます。この1年の5大事件をあげるとすればどうなるでしょうか。そこでは喜ばしい事だけでなく、おそらくはそれ以上に、厳しいこと、苦しいこと、不安を抱かせられることを数えることになるのではないでしょうか。世間においては新しい希望を見出すことができなかった1年を振り返りながらクリスマスを祝う、そこでなお喜びの根拠を見出すためにです。
また、この時季になると喪中のために新年の挨拶を失礼しますという便りが届きます。それを見ながら、あの人も亡くなったのかとしみじみと思わせられます。そうした便りを出す人にとっては、愛する家族を亡くした寂しさが込みあげてくるときかもしれません。そうしたときに――私は喪に服しているのでクリスマスおめでとうと言うことは失礼します、とは言いません。むしろ、悲しみや寂しさを覚えたままでクリスマスを喜び祝うことをクリスチャンは大切にしてきました。それはなぜなのか? その答えがマリアとエリサベツの喜びの姿の中にあります。
二人は自分たちを取りまいている社会の状況を喜んだのではないし、喜べる状況でもありませんでした。子を身ごもることそのものを幸いなことだと喜んだのでもない。二人にとっての身ごもりそのものは、やはり不可解なことでした。
二人は何よりも神さまがおられることを喜びの根拠としていました。そうであればこそ不可解な身ごもりも、神さまが約束を果たしてくださった証拠として喜ぶことができたのです。ここに待降節の喜びが現れ出ているということができます。その喜びをマリアはこう言いあらわしました。
「私のたましいは主をあがめ、私の霊は私の救い主である神をたたえます。」
ここで注目すべきは、マリアが「私のたましい」「私の霊」と言っていることです。「心」から主をあがめ、「心」から救い主をたたえます、と言ってもよさそうなものですが、「たましい」「霊」という言葉が語られていることを軽く聞き逃すわけにはいきません。このマリアの言葉についてマルティン・ルターが次のように述べていることが良い示唆を与えてくれます。
マリアのこの言葉は、強い情熱とあふれる喜びから発せられたものであり、そこへとマリアの全精神と生活とは、聖霊によって内的に高揚されている。それゆえに、マリアは「私は神を高くする」とは言わないで「私の魂は」と言っている……。なぜなら、喜びをもって神を讃美するということは人間の行為ではないからである。それはむしろ喜ばしい受動であり、ただ神のお働きによるものである。
(聖文舎『ルター著作集4』マグニフィカート・マリアの讃歌講解より)
ルターが言おうとしていることは、「たましいが主をあがめる」ということが実際に起こる場合、それは神さま(聖霊)の働きによるものであるということです。そのような説明を聞いてどう思われるでしょうか。大げさだと思うでしょうか。神をあがめ、ほめたたえることは私自身がすることなのだから、結局のところは私の決心によるのではないのか。それを神さまの働きとするのは少々言い過ぎではないか。マリアは困難の中で、主をほめたたえることを選び取り、主をほめたたえる決心をしたと言ってもよいのではないか…… そういう意見もあるかもしれません。そこで、マリア自身がたましいによって主をあがめ、霊によって救い主をほめたたえているその理由について語っている言葉に注目したいのです。
「この卑しいはしために 目を留めてくださったからです。」
「卑しいはしため」という言葉には、マリアが日々の生活の中で舐めている生きる厳しさ、辛さ、貧しさ、悲しさが込められています。その現実はマリア自身には変えようがありません。マリアは、謙遜をあらわすために自分のことを「卑しいはしため」と言っているのではないのです。
その卑しいはしためという状況の中で、マリアのたましいは主をあがめました。「あがめる」とは、神さまを大きくすること、すなわち恵みの神さまを大きく受けとめることです。そうしてこそ神さまを救い主としてたたえ、讃美することができるのです。
マリアが「卑しいはしため」という言葉で言いあらわしている生きる厳しさ、辛さといった現実は私たちにもあること、起こりうることです。たとえば、健康上の闘いや不安があります。肉体が痛むことはまことに辛いことです。この痛みさえなくなってくれれば……と思うこともあります。そうした肉体の現実をパウロは「卑しい体」(ピリピ人への手紙第3章21節)と言いました。想像してみてください。数時間に及ぶような手術を受け、集中治療室で何本もの管につながれて横たわり、死と向き合うような状況のなかで主をあがめること、恵みの神さまを大きく受けとめるということは、自分が決心さえすればできることなのでしょうか。
マリアが「卑しいはしため」と言いあらわした言葉に込められている生きる厳しさ、辛さ、貧しさ、悲しさをもたらす現実を前にするとき私たちの心は疲れ、不安に苛まれます。鬱々とし、あらゆる行為を停止させてしまいたくなります。嘆き、怒りに心が支配されてしまうこともあります。そうなったら主をあがめるどころではありません。そのような状況の中で主をあがめることができるとすれば、それは人間の行為でなく神のお働きによるものだというルターの説明は決して大げさなものではないといえましょう。マリアは自分が決心する以上のことによって、つまり神さまの働きによって見出していた喜びを語ったのです。
――神さまは私に目を留めてくださいました。身分の低い、まことに小さな、弱い、貧しい存在でしかないこの私に!
このマリアの喜びが根拠としているのは、マリアに眼差しをむけておられる神さまそのものにほかなりません。マリアのような存在に眼差しを向けておられる神さまのことばを旧約聖書のイザヤ書から聞きとることができます。
わたしの目には、あなたは高価で尊い。わたしはあなたを愛している。(第43章4節)
卑しいはしためという境遇にあるマリアを神さまは高価で尊い存在としてごらんになります。この神さまのアイコンタクトがマリアの喜びの根拠であり源泉でした。そしてこの聖なるアイコンタクトを感知させるものこそは神さまのお働きによる恵みなのです。
『マリアの讃歌』と呼ばれるマリアの言葉を、私たちが自分自身の言葉として生きることができたら、それはどんなにさいわいなことでしょう。そのために必要な神さまの働き、聖霊の助けを祈り求めたく思います。その際に、私たちができることとして、私たちの卑しさに目を留めてくださる神さまの眼差しを信じてまいりましょう。そして、卑しさにこそ目を留めてくださる神さまが実現してくださる救いを待ち望みたいと思います。
(2025年12月7日)