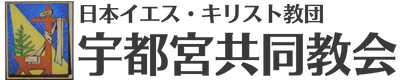降誕後主日・年末の礼拝
今週の金曜日は大晦日です。壁には2021年のカレンダーが役目を終えて外されるばかりになっています。もう既に2022年のカレンダーにかけ替えているという人もあるでしょう。
私たちはカレンダーを見て、日付を数えながら生活をします。ところが小さな子どもは、カレンダーを見ても正しく日付を数えることが出来ません。娘が保育園に通っていた頃、遠足が近づいてくると聞いてきたものでした。――お父さん、あと何回寝たら遠足の日になるの。教えて……この子どもの問いと似た言葉を今朝の聖書から聞きとることができます。
どうか教えてください。自分の日を数えることを。
そうして私たちに、知恵の心を得させてください。
(12節)
「自分の日」とは、自分が今まで生きてきた日、そしてこれから何年生きるかわからない残された日といってもよいでしょう。それを数えるとはどういうことでしょうか。また、そうすることで得られる知恵の心とはどのような知恵でしょうか。
今、私は57歳です。自分が生きてきた57年という年月をどういうふうに数えることができるか、その数え方が問われるのです。――私はもう57歳。まもなく60歳になる。早いものだ。人生の曲がり角はもう過ぎた。歳をとるのはいやだなあ……もし、そんなふうに考えてしまうならば、それは「自分の日」の数え方を間違っているといわざるを得ない。そのような間違った数え方をしてしまいやすいからこそ、聖書の詩篇は一つの祈りを示してくれているのです。
どうか教えてください。自分の日を数えることを。
――ああ、70歳、80歳だ……年をとるのは嫌だなあ……と思いながら自分の日を正しく数え損なってしまうのには理由があります。その理由とは、私たちは死を受けとめようとするときに、命のはかなさということを思うことです。命のはかなさを思うということは誰にでもあります。聖書も人の命のはかなさを決して無視しているわけではありません。それどころか、そのはかなさを次のように実にはっきりと言いあらわしています。
まことにあなたの目には
千年も昨日のように過ぎ去り
夜回りのひと時ほどです。
あなたが押し流すと
人は眠りに落ちます。
朝には草のように消えてしまいます。
朝、花を咲かせても移ろい
夕べにはしおれて枯れています。
(4~6節)
この詩篇第90編は、葬儀の時によくとりあげられて朗読されます。実際にこの詩篇が葬儀で朗読されたならば、それを聴いた参列者のなかには人の命のはかなさを思い、この詩篇の言葉に共感する人も多いことでしょう。しかし、そのような、人の命のはかなさを覚えるだけでは、自分の日を数えるためには足りないのです。何が足りないのか。そのことを見出すために、続けて次の言葉に耳を傾けて行きましょう。
私たちはあなたの御怒りによって消え失せ
あなたの憤りにおじ惑います。
あなたは私たちの咎を御前に
私たちの秘め事を
御顔の光りの中に置かれます。
私たちのすべての日は
あなたの激しい怒りの中に消え去り
私たちは自分なの齢を
一息のように終わらせます。
私たちの齢は70年
健やかであっても80年。
そのほとんどは労苦とわざわいです。
瞬く間に時は過ぎ
私たちは飛び去ります。
(7~10節)
この詩篇の作者が生きた時代、70歳というのはかなり長生きをしたといえるでしょう。ましてや80歳ともなれば、これは特別に長生きをしたということになります。
しかし、その特別ともいえる長寿による生涯を神さまが怒りをもってしかごらんにならないとしたらどういうことになるか。長生きをして、たくさんの良いことがあったとしても、どれほどの名誉や地位を得たとしても、もし神さまから――あなたのことを知らない。あなたのしてきたことを私は喜ばない……と言われてしまうならば、命の短さをはかなむどころではなくなってしまいます。
今朝の聖書は確かに人の命がはかないものであることを認めています。ただしその理由は、人の命には限りがあって短いからというのではないのです。そういうことよりももっと深刻な理由がある。それは、私たちの生涯は、神さまに喜んでもらえるような美しい生き方に満ちているわけではないということ。罪に汚れた日々が私たちの生きてきた日にはたくさんあり、人には知られたくないような恥ずかしい生き方をしてきてしまった日々が自分の生涯の汚点として残されている。そのような汚点としての日々に神さまが目をとめられたら、そう思うと自分の日を数えられなくなってしまう。そのことが、はかなさを通り越して深刻な恐れを呼び起こし「私たちはあなたの御怒りによって消え失せ あなたの憤りにおじ惑います」とまで言わざるを得なくさせているのです。
そのことをはっきりと語っている詩篇の作者ではありますが、だからといって苦く重く、打ちしおれていたというのではありません。自分の生涯が汚れと恥の数々に満ちていることを神さまはお見通しである。そのことを知りながらも、詩篇の作者は、その神さまに対して「主よ、世々にわたって あなたは私の住まいです」(1節)と信仰を言いあらわしてもいるのです。そして更に、こう祈ります。
朝ごとに
あなたの恵みで私たちを満ちたらせてください。
私たちのすべての日に
喜び歌い、楽しむことができるように。
どうか喜ばせてください。
私たちが苦しめられた日々と
わざわいにあった年月に応じて。
(14~15節)
詩篇の作者は「主よ」と呼びかけています。旧約聖書の信仰に生きた人たちが想い起す歴史の原点のひとつに『出エジプト』があります。エジプトで奴隷になって苦しんでいた人々が、神さまによってエジプトを脱出し救い出されたときから、解放された人々は神さまを「主」と呼ぶようになりました。「主」とは神を信頼して呼ぶ呼び名です。
しかも、その主なる神さまは、代々にわたってかわることのない住みかであるという。ここを外国語の聖書の中には「避難場所」と訳しているものがあります。危険が迫ったとき、ここに逃げ込みさえすれば安全という場所です。出エジプト以来、主であるお方はイスラエルのための住みか・避難場所であってくださったという信仰が「住みか」という言葉には込められています。
こうしてこの詩篇の作者は、イスラエルの歴史を支配し、イスラエルを決してお見捨てにならない神さまを想い起しながら、罪深い者を受け入れ、不信仰な者のために避難場所となってくださる主なる神さまを見出しています。その主に信頼して、ありのままの自分をまるごとお任せする。そうすることで、罪深い日々を生きてきてしまったことによる命のはかなさを安心して受けとめることができたのです。
今、申しあげましたことを要約して手短に言いましょう。私たちの「自分の日」は確かにいろいろな汚れや恥に満ちたものとなっています。そのような日々を生きてきた者に対して、それでも神さまは怒りの目ではなくて、あわれみの目を向けていてくださいます。その神さまのあわれみを知ることで、人は「自分の日」を安んじて数えることができる心とされる。それこそがこの詩篇が語っています「知恵の心」であります。
先週、私たちはクリスマスを祝いました。飼い葉桶の中に寝せられ、天使が讃美と共にその誕生を告げ知らせた幼子は、神さまが私たちを罪から救うために与えてくださった救い主であるということを聞きました。ここに、神の深いあわれみによる愛が示されました。ですから今、私たちが「自分の日」を正しく数えるために必要なことは、神の愛そのものであるキリストを想い超すことから始まります。クリスマスの出来事を想い起すことが私たちにとっての、自分の日を正しく数えるための第一歩となります。その実例を紹介しましょう。
クリスマスになると毎年のように読む書物があります。ヘルムート・ゴルヴッツァーという人が書いた『俘虜記―欲せざる国に引かれて行く―』という本です。
ゴルヴッツァーという人はドイツの牧師で、第二次大戦中、ナチスに抵抗する働きをしていたため捕らえられた人です。逮捕された後、国防軍の看護兵としてロシア戦線に送られ、敗戦と同時にソ連によりシベリアに抑留俘虜となりました。
その最初の年、1945年のクリスマスのことです。強制労働収容所内でクリスマスのお祝いが計画されました。その計画に対して激しい反対の声があがりました。収容所を管理するロシア人が、クリスマスを禁じたからではありません。意外なことにドイツ人の中から反対の声があがったのです。望郷の思いに打ちひしがれた一人がゴルヴッツァーに泣きつくようにしてこう言ったのでした。
「せめて考えないこと。せめて思い出さないこと。それだけが、俺のもちこたえてゆく手だてなんだ。お前さんたちがクリスマスのお祝いをしたりしたら、俺はもう生きられない。首をくくって死じまう……」
しかし、この男は首をくくりませんでした。<思い出さないこと>ではなく<全力でクリスマスの出来事を思い出すこと>で、男たちは暗黒の中に輝くクリスマスの光りを見たからです。
強制労働のためにシベリアに連れてこられた人々にとって「自分の日」を数えることは、はかなさを通り越して絶望でしかありませんでした。しかし、このクリスマス・イブの夜に起こったことについてゴルヴッツァーは言うのです。
「私たちの前に帰国があろうと凍てついた墓があろうと、この辛い道はいのちへと通じているのだ。クリスマスがある以上、それは確かだ。これは私たちから何人も奪い去ることはできない。そう思うと、ほっと息をついた」
こうして、ゴルヴッツァーとその仲間の男たちは、収容所のバラックの中にいながらにして、神が変わることなく自分たちのすみか・避難場所であることを見出したのです。
大晦日を控えたこの礼拝に集まっている私たちにとっても、自分の日を正しく数えるために欠かすことの出来ないことは、クリスマスの喜びに留まり続けることです。天使が告げて言った「あなたがたのために救い主がお生まれになった。この方こそキリストです」というこのクリスマスの出来事を思い起こしながら、大晦日を過ごし新年を迎えるのです。
年末を迎えて今なお、困難が残されているという方もあるでしょう。いったい自分のこの年の努力は何だったのだろうか、とむなしさや疲れを覚える方もあるかもしれません。新しい年に期待を抱きながらも何も変わらないのではないか。あるいはもっと厳しくなるのではないかと不安を抱かれる方もあるでしょう。だからこそ、神は私たちの住まい・避難場所であることを保証するためにキリストを与えてくださいました。そのキリストのご降誕、聖夜の出来事を想いながら、今こそ、ふさわしい讃美歌を、『きよしこの夜』を歌おうではありませんか。
(2021年12月26日待降後主日礼拝)
参考 ヘルムート・ゴルヴィッツアー著「不慮記―欲せざる国に引かれゆく」小塩 節訳(1974年 白水社)